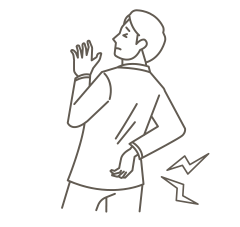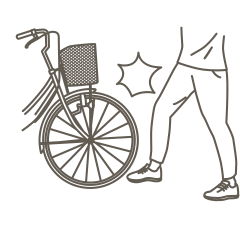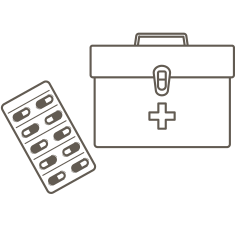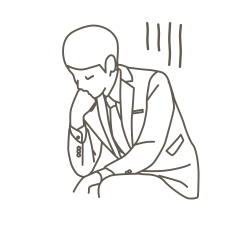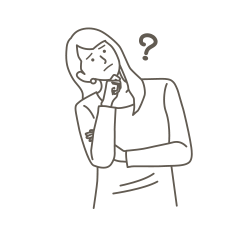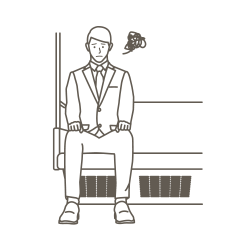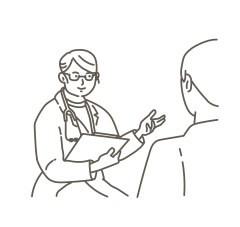- HOME>
- 健康を保ちたい
「ロコモティブシンドローム」(運動器症候群)への対策

厚生労働省は2023年7月28日、令和4年簡易生命表を発表しました。平均寿命(2023)が男性 81.05歳、女性87.09歳で、2年連続で前年を下回る結果でした。一方、健康寿命は男性72.7歳、女性75.4歳、で、高齢時代や要介護状態が長期化しているといえます。
「健康寿命」とは、人が「健康に生きていられる期間」のことです。現在、国が公表している「健康寿命」では、“健康”を、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できている状態と定義し、この定義に基づく健康寿命を厚生労働省による「国民生活基礎調査」の結果を使って3年ごとに算出しています。
65歳以上の方の死因別の死亡率を見ると、「悪性新生物(がん)」が最も高く、次いで、「心疾患(高血圧性を除く)」「老衰」が続きます。
当院では、この「老衰」の予防と改善を目標にしております。
「ロコモティブシンドローム」(運動器症候群)、略して「ロコモ」。これは近年注目され始めた用語で、「運動器の障害のために自立度が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態」を指します。日本では、実に毎年5万人もの人が「運動不足」が原因で亡くなっており、喫煙、高血圧に次いで第3 位との報告もあります。また、今後、高齢化が急速に進展する中、健康寿命を延ばし、できる限り日常生活に制限なく生活を続けられるようにするためには、介護予防などを通じたロコモ対策は極めて重要です。
当院では、マシーンを使用した大腿四頭筋訓練、適正な歩行補助具の選定、骨粗しょう症の早期発見と早期治療、転倒予防、リハビリテーションにより、「ロコモ」や「要介護状態」の回避を急務と考え、これらを行っております。
参考資料
●厚生労働省「健康寿命の延伸に向けた最近の取組み」
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-03.pdf
●内閣府「高齢期の暮らしの動向」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/html/zenbun/s1_2_2.html
生活習慣病予防・アンチエイジングの自費診療も実施
また、中高年からの生活習慣改善が死亡率低下と健康寿命の延伸に必要となって参ります。当院では、健康診断をはじめ、かかりつけ医として疾患の早期発見に尽力しております。
そして、若年中年層の疲労回復ストレス改善や抗酸化作用による生活習慣病予防・アンチエイジングの自費診療も行っております。若い時からできる限りの老化防止をいたしましょう。
生活習慣の見直しが重要
その1【運動】 適度な運動を毎日続けよう

まずは今より10分多くからだを動かすことから始めましょう。10分歩くと約1000歩!
無理しない程度に、毎日続けることが大切です。
その2【たばこ】 今すぐ、禁煙を!

多くの有害物質を含むたばこは、がんをはじめ、健康にさまざまな悪影響をもたらします。
また煙の害は喫煙者のみならず、周囲にいる人にも及びます。
その3【食事(塩分)】 塩分は控えめに

塩分は、1日男性7.5g未満、女性6.5g未満の摂取が適量です。
高血圧や動脈硬化を予防するためにも、塩分控えめの食事を心がけましょう。
また、すでに高血圧が疑われる人は、1日6g未満にしましょう。
その4【食事(脂質)】 油っぽい食事は避ける

油を使った食事はなるべく控えましょう。
肉類は「下ゆで」や「湯通し」するなど、調理法にも工夫しましょう。
その5【食事(肉類よりも魚のすすめ)】主菜は“肉より魚”を心がける

魚に含まれる油には、コレステロール値を低下させる働きがあります。
毎日の食事に、魚料理を積極的にとりましょう。
その6【食事(野菜)】野菜をたっぷりとる

野菜に含まれる食物繊維には、コレステロール値を低下させる働きがあります。
なるべく1日に350g以上とりましょう。
その7【飲酒】お酒はほどほどに

お酒は中性脂肪を増やしやすいので、飲み過ぎには注意しましょう。
1週間に1日は休肝日をもちましょう。
その8【歯の健康】毎食後歯を磨こう

むし歯や歯周病は自覚症状がないまま進行します。
予防には、毎食後のていねいなブラッシングが効果的です。
その9【ストレス】自分に合った方法でストレス解消

ストレスは、健康のバランスを崩す原因にもなります。
自分に合ったリラックス方法を見つけて、早めに解消しましょう。
その10【睡眠】規則正しい睡眠で十分な休養を

睡眠には、疲れた身体をリラックスさせ、疲労を回復させる効果があります。
夜ふかしを控え、規則正しい睡眠をとりましょう。